映画との出会い と イ ン ド
「熱い灰」 インドで撮影した私たちの映画第一作から紹介していきます
予告編 制作中
|
2009年この映画の制作開始 そうして地球はなくなるの ?
映画の世界に魅せられて、何の役にも立たないかもしれないと思いながらもしつこくやってきました。 派手な映画は創れませんが自分の映画をめざしています。 時間の流れは早く、 大切な仲間も何人 もいなくなりました 呑気なことを考えている歳ではありません。 梅原 猛さんが書いていました我々は 宗教 [ 神 ] を失った時代に生きている、それによって道徳も失っているんじゃないかと言っています。 日々のニュースを見ていると納得します 少年時代 毎日見ていた 爺ちゃんの畑・空・海・山 鹿児島本線 の汽車に大きな夢を見ていました そうだ とりあえず 今制作している 映画をすべて予告編にしようと、 いい加減な頭で考えました。 前々からこの 映画創りをインドで撮影した [熱い灰] [風の宴] 今創りたい と考えている [そぅして地球はなくなるの?] を三部作にしたいと考えています。 完成するかどうかは 判りません。 [予告編 1 そぅして地球はなくなるの?] 40分、[予告編2 音楽版] 10分、この時間は、 心に残っている音楽が、詩 俳句等もそうだと思います、3分から6分のもっと短い時間で心に残る音楽 を沢山残しているということが羨ましく、矢作 木の実さんに ピアノで 参加していただきました、 [予告編 3 ルバイヤート版] 12分 長谷川時夫さんにルバイヤートを唄っていただきました。 [予告編 4 大池ライブ版] 10分 長谷川時夫さんの十日町大池での雪の中のライブです、 [予告編 5 動物と 人間の話版] 20分 2014年から動物 11匹を看取りました, 1969年に 録音された 羽仁五郎さん・ 野坂昭如さん・ 大江健三郎さん・ 新崎盛暉さん・ 中野好夫さんの テープがでてきました、これは ゴミにはできない動物達の供養だと思い予告編5になりました。 [予告編 6 漆塗師 成田和雄 新潟 村上版] 13分 [予告編 7 西 武喜 百寿の宴 熊本版] 11分 [予告編 8 なみねこの会とサビ猫 千和]30分この歳になって猫を保護することになりました、 動物の一匹も面倒見れなくて人間かと いう思いがあり、出会った方々も素晴らしくこれは映画にしなければ・・・ まだまだ予告編は続くかも しれません、最後は2時間前後の本編です、 構想だけは大きく持とうと考えています。 地球温暖化 貿易センタ-ビル崩壊・大地震・コロナ・ 豪雨と 思えば 短い人生のなかでも次から次へと、これで もかと試練が襲いかかっています。 この先も残念ながら、いろんなことが襲い掛かってくることで しょう。地球も我慢できねーと困り果てていま。私もそうです、 私もこの歳なんだから、もう勘弁して よと思いますが、勘弁してはくれないでしょう。 この地球で、 決して忘れない、 しつこく生きる、 古い物を大切に受け継ぐ。 公平な社会を創る 私達に出来ることは沢山あります、 全ての 自給自足・地産地消しかないんじゃないかと考えています。 自分を守る、 体を鍛える、 忘れ ない、 仲良くする、 希望は捨てない、 皆さんもくれぐれもご自愛ください。
『ガンディー魂の言葉』 から抜粋 現代社会に巣食う七つの大罪とは……。 理念なき政治 労働なき富 良識なき快楽 貢献なき知識 道徳なき商業 人間性なき科学 献身なき信仰 |
|
|
|
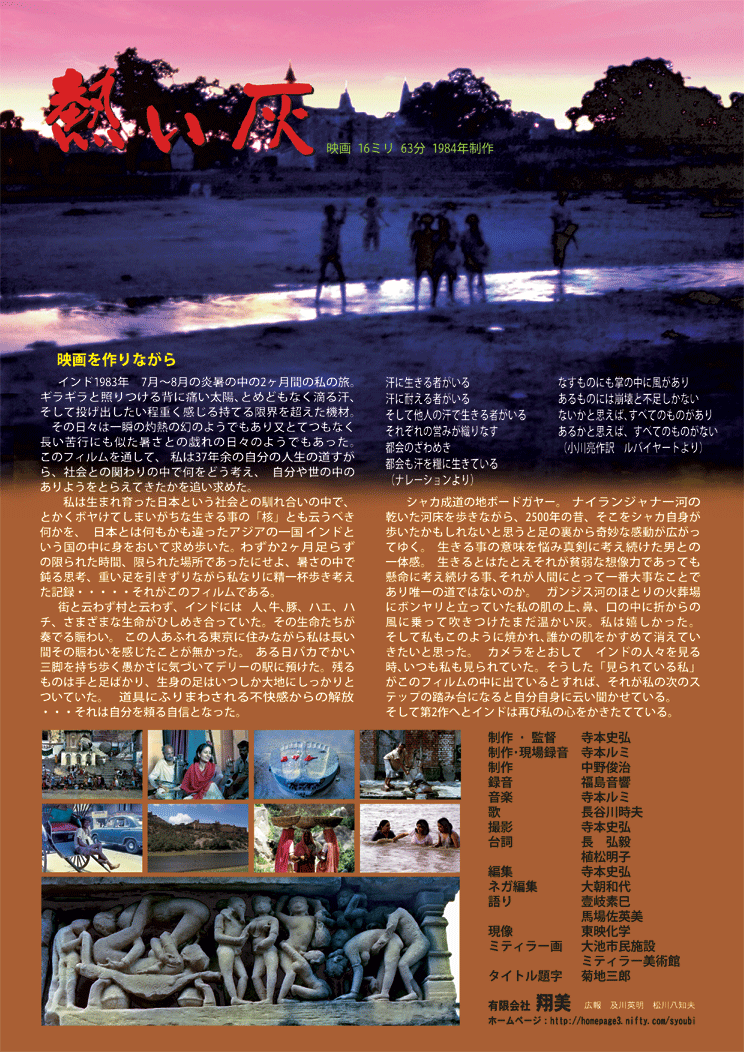
|
|
|
|
|
|
インド1983年7月〜8月の炎暑の中の2ヶ月間の私の旅。ギラギラと照りつける背に痛い太陽、とめどもなく滴る汗、そして投げ出したい程重く感じるカメラ。 その日々は一瞬の灼熱の幻のようでもあり又とてつもなく長い苦行にも似た暑さとの戯れの日々のようでもあった。 このフィルムを通して、私は37年余の自分の人生の道すがら、 社会との関わりの中で何をどう考え 、自分や世の中のありようをとらえてきたかを追い求めた。私は生まれ育った日本という社会との馴れ合いの中で、とかくボヤけてしまいがちな生きる事の「核」とも云うべき何かを、日本とは何もかも違ったアジアの一国インドという国の中に身をおいて求め歩いた。 わずか2ヶ月足らずの限られた時間、限られた場所であったにせよ、暑さの中で鈍る思考、 重い足を引きずりながら私なりに精一杯歩き考えた記録それがこのフィルムである。 街と云わず村と云わず、インドには人、牛、豚、ハエ、ハチ、さまざまな生命がひしめき合っていた。 その生命たちが奏でる賑わい。 この人あふれる東京に住みながら私は長い間その賑わいを感じたことが無かった。 ある日バカでかい三脚を持ち歩く自分の愚かさに気づいてデリーの駅に預けた。 残るものは手と足ばかり、生身の足はいつしか大地にしっかりとついていた。道具にふりまわされる不快感からの解放―――それは自分を頼る自信となった。 |
|
汗に生きる者がいる 汗に耐える者がいる そして他人の汗で生きる者がいる それぞれの営みが織りなす都会のざわめき 都会も汗を糧に生きている ナレーションより カジュラホ村に一人のヘビ使いを見た。小さな素焼きの壷の中から出て来たボロボロのヘビを見た。 笛吹けど踊らず。それでも懸命に笛を吹く若者。懸命に逃げようとするヘビ。だが最後にヘビは踊った。
一人と一匹の仲は結構しっくりいっているように見えた。 |
|
なすものにも掌の中に風があり あるものには崩壊と不足しかない ないかと思えば、すべてのものがあり あるかと思えば、すべてのものがない 小川亮作訳・・・ルバイヤートより |
|
シャカ成道の地ボードガヤー。ナイランジャナー河の乾いた河床を歩きながら、2500年の昔、そこをシャカ自身が歩いたかもしれないと思うと全身に奇妙な感動が広がってゆく。 生きる事の意味を真剣に考え続けた男との一体感。 生きるとはたとえ貧弱な想像力でも懸命に考え続ける事、それが人間にとって一番大事なことであり唯一の道ではないのか。 ガンジス河のほとりの火葬場にボンヤリと立っていた私の肌の上、鼻、口の中に折からの風に乗って吹きつけたまだ温かい灰。 私は嬉しかった。 そして私もこのように焼かれ、誰かの肌をかすめて消えていきたいと思った。 カメラをとおしてインドの人々を見る時、いつも私も見られていた。そうした「見られている私」がこのフィルムの中に出ているとすれば、それが私の次のステップの踏み台になると自分自身に云い聞かせている。 そして第2作へとインドは再び私の心をかきたてている。 |
|
熱い灰 16ミリ63分 製作 寺本プロダクション |
|
製 作・監 督・・・・・寺本史弘 |
歌・・・・・・・・・・・長谷川時夫 |
語り手・・・・・・・・・壹岐素巳/馬場佐英美 |
Copyright 2002 My Company. Syoubi C.Center